| 松川陣屋墓地の外観 |
| 遠くに日光の連山、近くには筑波山の峰を望み、眼下に涸沼を見下ろす絶景の地にあります。友常石材より、供養と安らぎの心を込めて、ご提供致します。 |
 |
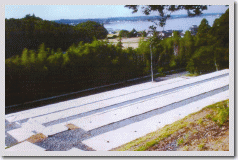 |
| 【墓地入り口】 |
【墓地内】 |
|
|
| 松川陣屋墓地の概要 |
| ◆所在地 |
茨城県大洗町松川 |
| ◆総区画 |
全200余墓 |
| ◆面積/1区画 |
3.6平方m(1.8m×2.0m) |
| ◆価格/1区画 |
永代使用料金 30万円
年間管理費 3000円
建墓石 180万円〜 |
| ◆受入可能宗派 |
宗派不問 |
◆管理・事業主体
(お問合せ先) |
松川陣屋墓地管理組合 木内政実事務局長
〒311-1136
茨城県水戸市東前3-24-2
TEL:029-269-6986
FAX:029-269-6986
<工事指定石材店>
友常石材株式会社
〒309-1635
茨城県笠間市稲田949
TEL:0296-74-2313
FAX:0296-74-3868
|
| ◆交通案内 |
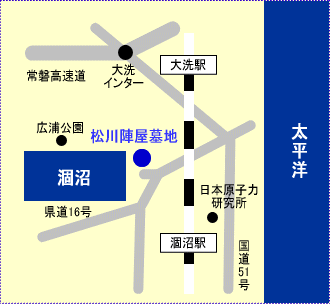
※常磐高速道 大洗インターより 約5分
※JR常磐線上野駅-(66分)-水戸駅-(17分)-鹿島臨海鉄道大洗駅より車7分 |
|
| 松川陣屋墓地の由来 |
松川藩は、本来守山藩と言われていました。水戸藩祖頼房公(徳川家康公の11男)の4男頼元公は、寛文元年(1661)に常陸額田の地を与えられ水戸新家を創立しますが、その子頼貞公の時、元禄13年(1700)、改めて幕府より奥羽と常陸に領地を与えられ、守山藩(2万石)が成立します。守山藩は水戸藩の支藩として、御連枝と呼ばれ、定府制で参勤交代はなく、藩主以下江戸大塚吹上の藩邸にいました。陣屋は、松川と守山(郡山市)に置かれ、郡奉行以下数名の藩士がいました。
守山藩政は、水戸藩の影響を受け、特に幕末の水戸藩内争や戊辰戦争時には、動乱の渦中に翻弄され、苦難の中を過ごしました。
慶応4年3月6代藩主は、一族郎党300余名を引き連れ、動乱の江戸をのがれて、松川に移りました。
明治3年(1870)、7代頼之公(徳川慶喜公の弟)の時、藩庁を松川陣屋に移し、松川藩と改称しました。しかし、明治4年の廃藩により松川県となりました。多くの藩士は東京や県外に移りましたが、一部の藩士は、松川に定住しました。その松川陣屋跡は、町道上の北西側台地にあります。
陣屋墓地は、藩の墓地として、側室及び藩士とその子孫の霊を祀ってきましたが、永年のうちに、巨木繁り、昼尚暗き有様に荒廃していましたので、平成13年に伐採整地し、墓碑を修復し、環境を整えたものなのです。 |
|